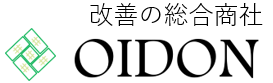タクシー業界を破壊するUber(ウーバー)を使ってみました
Uberは、スマホのアプリからタクシーの配車依頼ができるというアメリカ発のスタートアップのサービスです。
時価総額は625億ドル、日本円で約6兆3700億円であります。ホンダが約4兆5000億円、日産自動車が4兆2000億円と比べても、投資家からの評価は自動車会社よりも高い企業なのです。
一般の人がドライバー登録することができる新しいサービスのため、既存のタクシー業界が破壊されてしまうという懸念から世界各国のタクシー業界から反発をうけています。しかし、サービスの利便性の高さから業界からの反発に負けず拡大し続けています。
これほどまでに拡大しているUberとはどのようなサービスなのでしょうか。
今回アメリカへ出張の際に、話題のUberを使ってみました。
簡単にいえばスマホをクリックするだけで、行きたい場所に連れていってくれるサービスです。
まず、アプリをダウンロードします。アプリを起動し、クレジットカードや電話番号などの情報を入力します。
現在の場所から何処に配車をするかを地図上からクリックして選択します。その場所から何処に行くかを事前に入力します。
すると、今現在から何分ぐらいで待ち合わせ場所まで到着するか、目的地にいくら掛かるか、誰がドライバーで、どんな車が来るかが表示されます。あとは、車を待って、車に乗れば、目的地まで運んでくれるというプロセスです。
Uberのドライバーは、タクシーのライセンスを持ったドライバーではなく、一般の人が登録をしてUberのドライバーとなっています。Uberのドライバーは、他の業界で働くよりも簡単に稼ぐことができるので、爆発的に登録者数も増えています。ドライバー数の増加に従って、待ち時間がより少なく便利に使えるようになっています。
今回、7回程度Uberで移動しました。
郊外のレストラン、ショッピングセンターへの移動などタクシーを捕まえるのが難しい場所からの移動が簡単にできるので、とても便利なツールであることがわかりました。
タクシーであれば、場所を伝える事が難しい場所でも事前にアプリの地図上で住所を入れていれば、後はUberのドライバー側の地図で判断してその場所まで連れて行ってくれるので、コミュニケーションのストレスも全くありません。
途中レストランからホテルへ戻る際、Uberのアプリが起動できないトラブルに見まわれ、タクシーにも乗ったのですが、
・料金が高いし、ドライバーにチップが必要。しかも、配車をお願いしたレストランのスタッフにもチップが必要。行きはUberで$10程度だった道のりが、帰りは$20と倍の料金でした
・配車までの時間が30分かかった。Uberでは10分以上待ったことはなかった。
など、今回の出張では圧倒的にUberの方が利便性が高く、流行る理由がわかりました。
ただ、到着した空港からホテルへの移動に関してはやや不便なことが有りました。
空港から、市街地のホテルまでの移動でUberを使ったのですが、まず問題だったのが、待ち合わせする場所。
待ち合わせ場所を空港出口に設定したのですが、これが問題でした。4分以内に来る表示でしたが、なかなか来ない。途中で電話がかかってきます。今何処にいるかと言われたのですが、初めての場所なので自分の場所をうまく伝える事ができません。相手はtransportation centerにいるとのこと。今いる場所から、10分ぐらい移動してやっと、待ち合わせ場所までつきました。途中3回ほど電話のやり取りをしてやっと待ち合わ場所がわかり、待ち合わせ場所を見つけるのが大変でした。後でわかったのですが、空港では、Uberはある特定の場所でしか乗り合わせてはいけないという規則になっているようです。
しかも料金はタクシーに乗った時と同じ値段でした。空港から市街地までの料金はタクシーもUberも同一の値段でやっているのです。
これだったら最初からタクシーに乗っても良かったかなという印象です。
タクシーを捕まえるのが難しい場所から乗る場合に配車しやすいとか、やや複雑な場所を目的地としていてその場所を伝えることがなかなか難しい場合などはuberは圧倒的に便利に使えます。しかも料金はUberのほうが安い。ただし、空港からはタクシーはたくさんあり、また目的地もホテルなので簡単に伝えられるので、空港からの場合はUberはそこまで便利ではないということがわかりました。
日本では、まだ東京しかサービスはスタートしていません。日本でも日本語ができない海外からの訪日外国人等が使うようになって、uberドライバーの数が増えていけば、既存のタクシー以上の利便性を持つUberが今後日本でも流行る可能性を感じました。
※今回は、Uberという既存事業から反発を受けるような新しいビジネスモデルを取り上げました。改善においても、既存事業に反発を受けることでも、利便性の追求のために推進することも必要だと感じます。