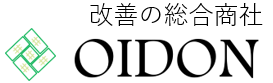かつてはメーカーの立場が強く、価格はメーカーで決め、その価格を消費者に小売りが提供する構造(メーカー至上主義)でした。松下電器(現パナソニック)も、販売店に値引き規制を掛けて安売りにならないようにしていました。
今は変わって来ていますが、まだまだメーカー(工場)の立場だと価格は、自社で決め、その価格で消費者に提供する考えに陥りがちではないでしょうか。
そういった中でも、かつてダイエーは消費者のための価格(安売り)を設定し、その価格でメーカーに良い品を製造してもらうという消費者のための価格設定(安売り)を行い消費者優位の流通革命を起こしました。
その結果、一代で連結売上三兆円を超える企業を築いた中内功氏。その著書の中から、メーカー至上主義に陥らないようにいくつかピックアップしてご紹介します。
☑消費者はコストとは無関係
中内氏はメーカー至上主義に対して「消費者の判断は、生産者の主観的な期待や思惑とは完全に独立した行動である。つまり、コストと無関係なのだ」と説きます。
確かにいくらメーカー側が良いものをコストをかけて作っても、最終的な消費者が欲しいと思う価格でなければ売れません。
よく改善を行う理由としても、我々は価格(売上)を変えることができないから「利益=売上-原価」のうち、原価をなるべく小さくして利益を稼ぐために改善しましょうと言います。消費者の欲しい価格で利益を出すためにも、改善し続けることがやはり大事なのでしょう。
もっともappleのiphoneのように価格(売上)を上げられる程、消費者にとって魅力的な商品を出すことも一つの利益を上げる方法です。
☑農業の工業化
ダイエーは小売り業でありながら「牛肉をつくる発想」をしました。牛肉を販売する過程で「牛肉を××円で売るためには、子牛をいくらの飼育費かけるかという考え方」をして、売値からの発想で利益の得られる飼育コストを割り出して、実際に牛を育て、肉にして、販売しています。
まるで、売値から、利益の出る製造コストを割り出して、製品を生産する工業と同じです。消費者の求める売値から飼育コスト(栽培コスト)を算出する工業的発想が進めば、儲かる農業へと変わりやすくなるでしょう。
| 消費者の求める価格に見直してはいかがでしょうか。それに応じて原価低減の改善に取り組むことで、商品の競争力は増していきます。 |
★昨今ではネット通販により流通業界は変わって来ていますが、本書「わが安売りの哲学」には、「商人の役割とは何か」「小売業の役割とは何か」「流通業の役割とは何か」という普遍的な哲学が詰まっています。是非ご興味ある方は、本書をご参考下さい。