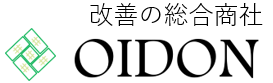日本酒(地酒)造りは、杜氏による職人のカンコツで作るイメージがあります。杜氏による目、舌、手触りなどなど、入社2~3年目の新入社員では関われない難しい仕事です。
そんなカンコツ作業を、杜氏に頼らず、新入社員でも関われる仕事にしたお酒があります。しかも海外でも絶賛される程美味しい日本酒「獺祭」で有名となった朝日酒造。代表の桜井氏は、どのようにして獺祭をつくったのか。「改善」の視点で、著書からいくつか抜粋してご紹介します。
☑徹底した数値管理
米を洗うとき、米の水分量を米の見た目で従来は判断していました。
それを、何度の水に何分つけたらよいのかを重量で計算することを行っています。その他にも、アミノ酸度、グルコース濃度など徹底した数値化により、誰にでも見てわかる酒造りをすることができました。
☑四季醸造による「ムリ・ムラ・ムダ」の排除
通常、温度的にも酒造りに効率的な冬に行います。
ただし獺祭は『冬と比べて夏に仕込むと少しは苦労しますが、それ以上に、優秀な製造担当者を正社員として年間雇用できる、もしくは設備の稼働率が飛躍的に向上するため原価率が下がる』ということで、冬に限らない四季醸造を行いました。
今までは冬に休みなく「ムリ」して大量生産することで、その他の季節に作らない「ムラ」が生じて、必要以上の設備・従業員を抱える「ムダ」が生じていました。俗にいう「ムリ・ムラ・ムダ」の3ムです。
この3ムを無くし、しかも小ロットで年間何回も生産可能になり、年間雇用できることになったので知識・ノウハウの蓄積されるように成功しています。
☑すべてが手本書(マニュアル)に出来るわけでない
著書では『「日本的なもの」とは、すなわち、「洗練」だと思います。カイゼンと言い換えてもいい』と語ります。数値化し、手本書を作って、新入社員でも仕事ができるようにしていますが、一方で、『最終的に解析しつくすことは不可能である』と語っています。
手本書(標準作業)を作ることは改善の第一歩になりますが、そこである程度の品質のものまではいきますが、「獺祭」のようにそれ以上目指す場合は、人間のカンコツも必要になります。
出来る限りは標準に落とし込みますが、『わからない領域がある、ということが理解できないと、本質はわからない』という桜井氏の言葉を理解する必要があるでしょう。
今日から出来る改善ポイント
| カンコツの作業は周りにありませんか。出来る限り数値化し、誰にでも出来る作業にし、作業を洗練(改善)させてみてください。 |
★本書「逆境経営」には、『つぶれそうだ』と言われた時期から、世界に展開する企業にまでのし上がった経営の秘密が改善以外にも書かれています。是非ご興味ある方は、本書をご参考下さい。