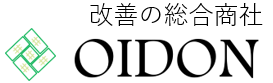改善定石 5定について(4C1S)
ものごとの整理のために5定について説明します。
1) 定路(Consstant Road)
改善の流れを作り方はまずは路(道)からであります。
物事を進める上でも、住むにも、良い事、良い街を創る時にも先ずは交通手段や経路を決めます。逆にいうと適当に家を建てた後から空いた所や最初に誰か通った所を道にすると、とても生活には不便になります。細くて曲がりくねったり交差点ばかりで停滞したり、見通しが悪くて事故が起きやすい道になる。解りやすく流れが良くなるには進む路が必要だけの広さがありムダが無く合理的に定めた経路を造る事です。
2)定置[定位置](Stationry)
次に位置を決める。
道が決まると道から必要な物を供給したり取りにいくための位置に設備やラインを設置していく。すると道からの出入り口が決まります。中で使うものは使う姿で置く。使う姿で置くと戻し易さも良くなるので位置が必然的に定まる
3)定名[定表示](ConstantName)
表示をする。
決めた場所が”ここはどこか”、そして物のところには”これはなにか”の表示をする。お店の看板の表示と中で働いている人の名札と同じで、表示が無いと”あそこの・・あれ・・・それ・・・あのひと・・”と仕事をしていくとミスが発生しやすくなる。
4)定量(ConstantVolume)
量を定める。
量が溢れると決めた位置に収まり切れなくなるので定位置が乱れる。無くなると困るので必要な分は置かなくてはならない。だから量も定める
5)定色(ConstantColor)
識別判断をする。
最後に色をつかって判断を正確にスピーディにしていく。
このように決めていくと定めた事で基準に対して”ムダ”の発生防止と”変化するムダ”である異常の「視える化」になる。
定めるといっても固定することではありません。売れる量や品番、さらにお客様も変化していくため、これにつられてムダも変化していく。そのため、いつでも変えられるように決める事が大切です。